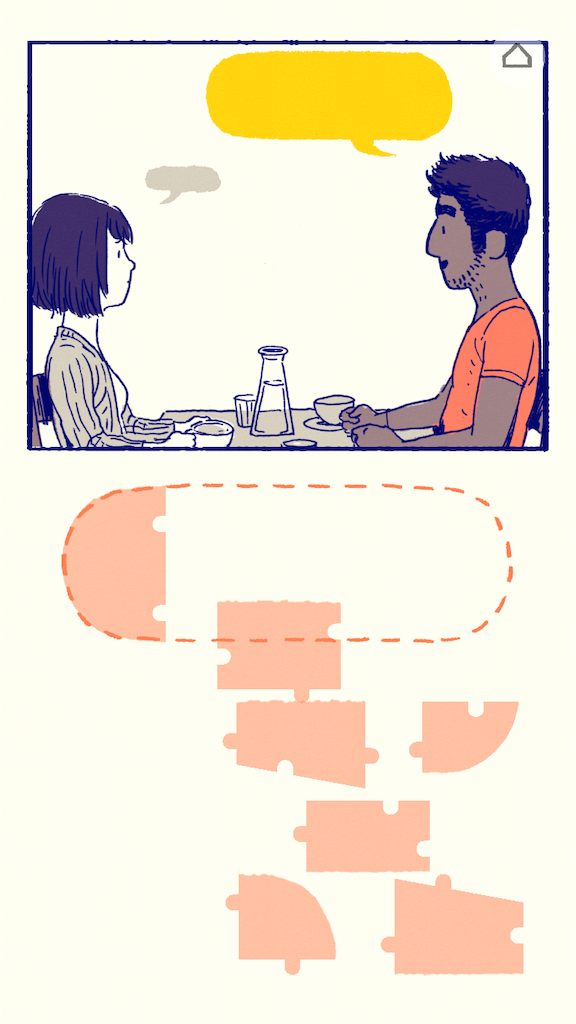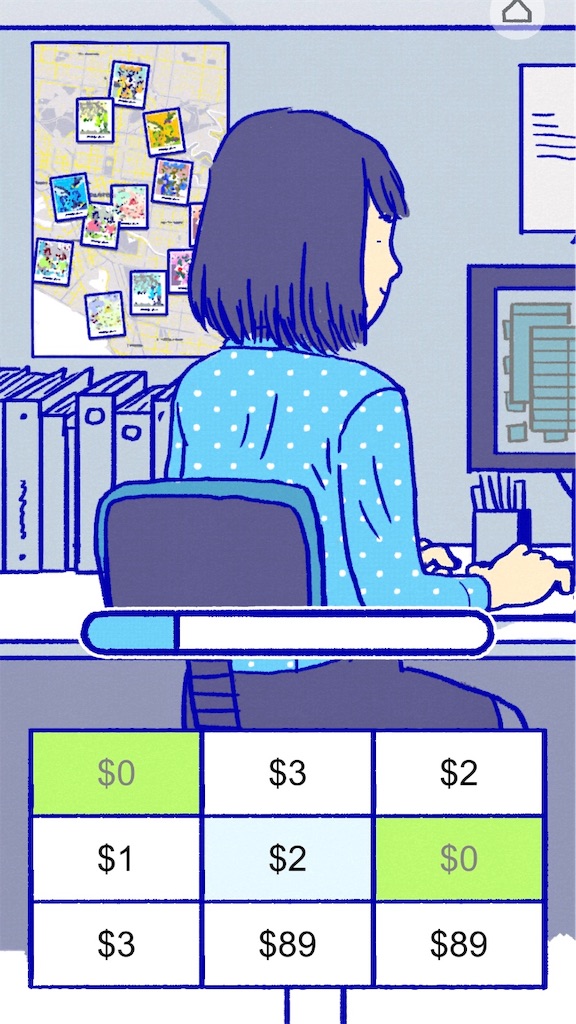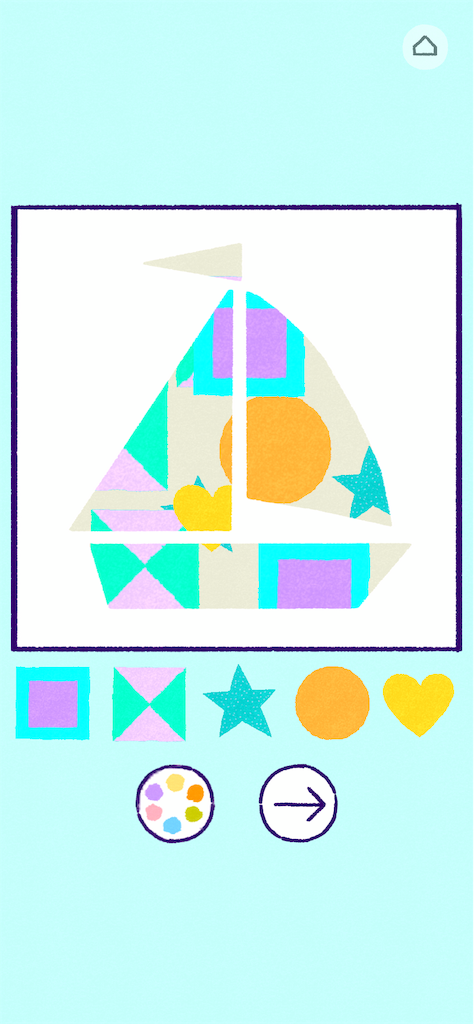※本記事では物語などのネタバレはしてません。
ニンテンドースイッチ版『オブラディン号の帰港(Return of the Obra Dinn)』をクリアした。一応攻略情報などはシャットアウトして、なんとか自力で60人全員の安否を解明できた。クリアまで10時間。とても素晴らしいゲーム体験だった。

このゲームは乱暴に言えば「5人の中で、1人だけ嘘つきがいます。彼らの話を聞いて、それは誰か当てましょう?」みたいな論理パズルの60人バージョンである。帰港した船舶オブラディン号には60人の乗客が1人も生きて残っていなかった。そんな状況で、主人公は不思議な時を巻き戻す懐中時計を使って、様々な情報を収集し、誰がどのように死んでしまったか、はたまた生きているのかを解明していくという筋書きになっている。
論理パズル的なゲームだが、自分が最後までクリアするにあたっては、全てがロジカルに答えを導き出せたわけではない。「4人まで絞ったけど、あとは分からん!」みたいな状況になり、総当たりで無理矢理答えを出してしまった部分も多い。ただ、そういう体験も含めて実に楽しかったことは間違いない。ちゃんと答えを論理的に導き出せなくても、答えだけでも当たっていれば「それでよし」としてくれるいい意味での"いい加減さ"がある。この"いい加減さ"はおそらく本作をより間口の広い作品にしているポイントなのではないかと思う。
また本作を論理パズルと表現してしまうと、若干違った印象を与えてしまうと思うのは、情報量の感覚についてである。いわゆる普通の論理パズルでは、情報というのは比較的過剰に与えられる。その過剰に感じられる情報をいかに整理して、相互に矛盾しないように並び変えるかが重要だ。しかし『オブラディン』では少し違う。本作では、前半部分で確かに大量に情報が与えられるものの、中盤から謎解きのための情報に飢えることになる。ここからがいわゆる「ゲームらしい感覚」と「物語世界を味わう感覚」の二面性が感じられる本作の醍醐味とも言える良さがある。
本作は中盤くらいで、基本的な情報は出そろう。しかしそれらの情報だけでは、到底多くの部分が特定できないのではないか?と、その全体像の見晴らしの悪さに茫漠とした気分をプレイヤーは味わう。情報が圧倒的に足りないように思えるのだ。ゲーム的にも辛さが大きくなっていくところで、ここで踏ん張れないとちょっとクリアまでいけないというケースはあるだろう。ここを先程の"いい加減さ"で突破するか、もう一つこの『オブラディン』特有の「情報を作り出す感覚」を楽しめるかが重要になってくる。
中盤以降の情報に飢えている状況で、実は地味に人物同士の関係性や場所の特性などが見えてくることがある。「この男はやたらコイツと一緒にいるな。ということは…」とか「コイツがこの場所にいることが多いということは、もしかして職業はこれか?」とか、実はこれまで情報だと思っていなかったことが、ヒントになってきたりする。こういう「観察によって情報を生み出す」感覚の面白さに気がつくと、『オブラディン』というゲームへの見方が変わってくる。情報の与え方の無骨さが、むしろ魅力にも感じられ、そこにある素っ気ない事実の塊が「わたしだけに見せる顔」のような官能さを生み出す。ここまでくると『オブラディン』はより愛おしいゲームになってくるだろう。
一部、死因が分かりにくかったりする部分もあるものの、そういう点も含めて、プレイヤーへの媚びなさが、この作品を彫刻のように削り取って自分だけの形にするような喜びにつながっている。ゴロッとした情報の原木が、次第に美しい彫像のような姿に変わっていくこの感覚。最初は全く馴染みも何もなかったはずの60人の一人一人の名前が、最後には全て知り合いの名前のように思えてくる。話の展開や内容などに大きな驚きがあるわけではないけれど、最後、60人の安否情報が綺麗に埋まったリストを見ていると、そこに単なるテキストを超えた余白の存在を感じ、なんとも言い難いゲーム独特の物語体験を味わうことになる。
ゲームでしか味わえない物語というものがあるとするならば、『オブラディン号の帰港 Return of the Obra Dinn』は、まさにそれを与えてくれる傑作の1本であるだろう。